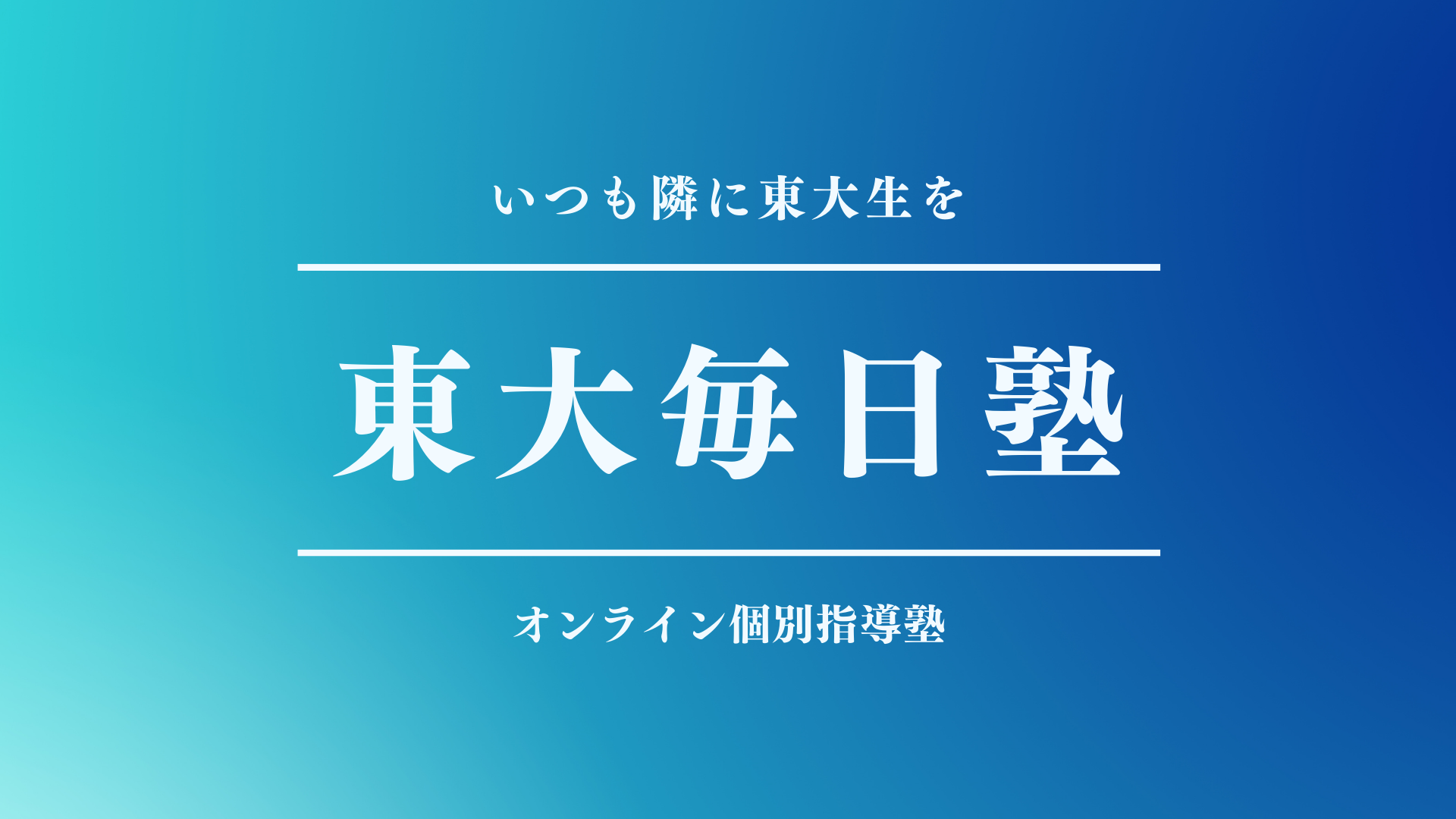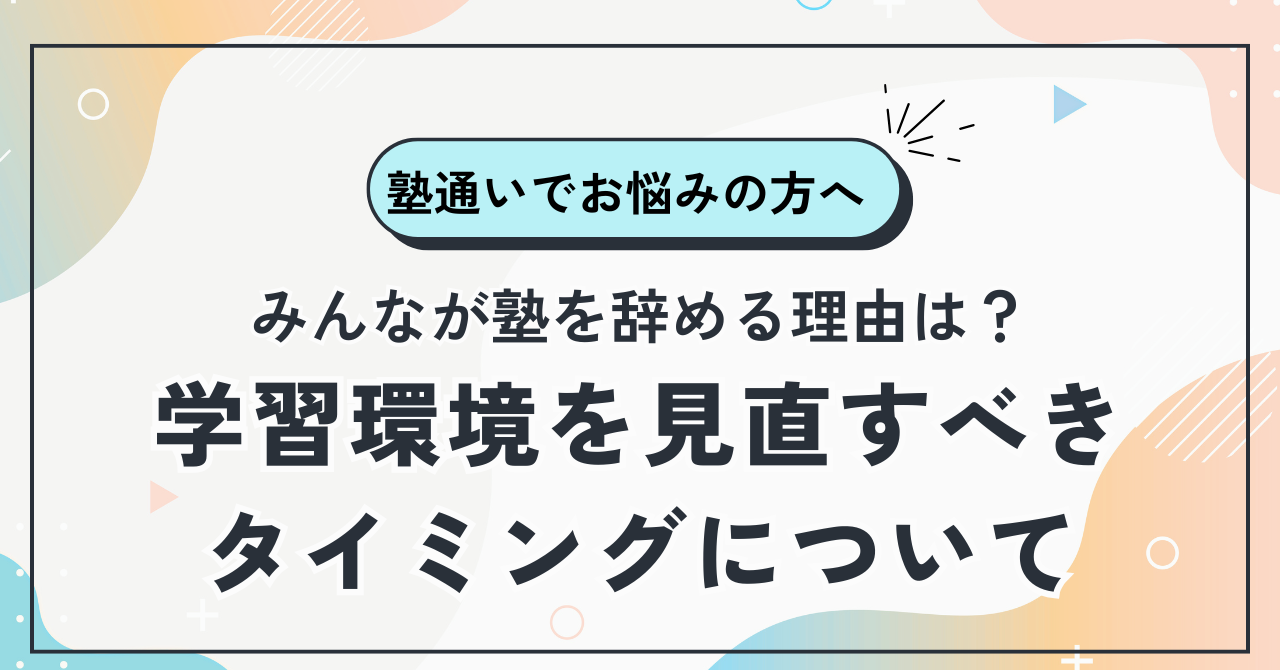全体として
・4、5文ただの文章が続いたら何かしら装飾できないか考えてみましょう。
まとめ的な文章の装飾、特定テーマの背景塗りつぶしやタイトルブロックなどが使いやすいです。
・急に何の話が始まったかわかりにくいところはタイトルブロックがおすすめです。

予備校に通っているけれど、もう行きたくない
浪人生活に疲れて、勉強に身が入らない
そんな気持ちを抱えているのは、あなただけではありません。
これまで1000人以上の受験相談に乗ってきましたが、このような相談をたくさん受けてきました。
- 毎日同じ場所で勉強を続ける生活
- まわりとの比較
- 思うように伸びない成績
この箇条書きはポイントなど目立たせたい箇所ではないので、囲みなどの装飾はしなくても大丈夫です。無理に全ての箇条書きで囲み装飾を適用する必要はないという理解でお願いします!
など受験勉強には、心が折れそうになる瞬間が誰にでもあります。
塾や予備校、自習室などに通うなかで、孤独やプレッシャーを感じ、「このままで大丈夫かな」と不安になることもあるでしょう。
「行きたくない」理由は人それぞれです。
- 授業がつまらない
- 先生が合わない
- 周りの雰囲気がなんとなく苦手
など、言葉にしづらい居心地の悪さを抱えていることも多いもの。
だからこそ、まずは状況を客観的に振り返り、次の一手を考えることが大切です。
本記事では、東大毎日塾塾長の私内田の見解のほか、東北大学に自宅浪人の末合格した佐藤さんにも実際の受験の体験談をお聞きし、予備校に行きたくなくなる理由やリスク、代わりの勉強スタイルを検討するポイントをまとめました。
なお、環境を変えたいと感じている方は、「受験のプロが毎日指導」をコンセプトとしているオンライン個別指導塾「東大毎日塾」を受験の勝率を高める選択肢としてご活用ください。
東大生メンターが丁寧に学習計画を作成・管理し、24時間いつでも質問できる環境を整備しているので、「もう予備校は合わない」と感じる方のお力になれるはずです!
\今だけ無料体験あり/
無料体験は毎月10人限定
↑普通の文章が5文続くので、何らかの装飾をしたいです。今回はテーマが切り替わる箇所をグループ化して塗りつぶしてみます。修正例↓
なお、環境を変えたいと感じている方は、「受験のプロが毎日指導」をコンセプトとしているオンライン個別指導塾「東大毎日塾」を受験の勝率を高める選択肢としてご活用ください。
東大生メンターが丁寧に学習計画を作成・管理し、24時間いつでも質問できる環境を整備しているので、「もう予備校は合わない」と感じる方のお力になれるはずです!
\今だけ無料体験あり/
無料体験は毎月10人限定
なぜ「予備校に行きたくない」と感じるのか?
予備校に通い始めたころはやる気があったのに、途中で足が遠のいてしまうのには、いくつかの理由があります。
ここからは、主な理由を7つに分けて紹介します。
学習面だけでなく、人間関係や経済的な負担など、多岐にわたる要因を見直してみましょう。
↑これが正解というわけではないのですが、1段落に複数の文章をまとめた方がみやすい場合もあります。同じ話題の時は縦に長くならなければ1段落にまとめた方が冗長になりにくいです。修正例↓
ここからは、主な理由を7つに分けて紹介します。
学習面だけでなく、人間関係や経済的な負担など、多岐にわたる要因を見直してみましょう。
学習ペースや指導方針が合わない
第一に考えられるのが、予備校のカリキュラムや授業のスピードが、自分の得意不得意や理解度に合わないケースです。
大手予備校は多数の受験生を対象とするため、平均的なペースで進むことが多く、得意科目が物足りなかったり、苦手科目が早すぎてついていけなかったりする場合があります。
また、指導方針が自分の学習スタイルと合致しないことも問題です。
たとえば、演習を中心に進めたいのに講義ベースばかりだったり、逆に理論を重視したいのに問題演習が多すぎると、モチベーションを保ちにくくなってしまうでしょう。
講師との相性が悪い
「分かりやすい」と評判の講師がいても、それが必ずしも自分に合うとは限りません。
講師の話し方や雰囲気、板書のスタイルなど、ちょっとした要素で「この先生の授業は聞き取りづらい」と感じることもあるはずです。
さらに、質問しづらい空気感や、忙しそうで声をかけにくい状況が続くと、疑問を解決しないまま授業が進行してしまいますよね。
こうした授業とのミスマッチが積み重なると、やがて「通っても成果が出ない」と感じ、足が遠のいてしまう要因になります。
授業のレベルが合わない・ついていけない
受験生の実力は人それぞれなので、クラス分けがあってもレベルの差が生じることは珍しくありません。
ハイレベルなクラスに入ると、周囲に合わせるだけで精一杯になり、自主的な復習や弱点補強が追いつかないまま講義が進む可能性があります。
逆に、レベルが低いと感じるクラスでは、簡単すぎて退屈になりがちです。集中力も途切れやすく、「ここに通う意味があるのか」と疑問を持つようになるかもしれません。
↑文は必ず改行しましょう。前のテーマが続くので段落はわけない方が良いかかと思います。
自分にぴったりのレベル設定は予備校選びの大切な要素です。
↑↑まとめ的な文言なので、こういう装飾もありです。
(ただの文章が4段落続くので、何かしら装飾できないかなという目線で見ていました。)修正例↓
勉強・通学疲れ
長時間の通学や満員電車によるストレスが加わると、家に帰ったころにはヘトヘトになってしまうこともあるでしょう。
勉強そのものが嫌いなわけではなくても、通学の負担が原因で「今日はもう行きたくない」と感じる日が増えるのはよくあるケースです。
通学時間を有効活用できる工夫をしても、移動自体に限界があるとストレスは拭いきれないかもしれません。
大学に進学した友達を見て、焦りや虚無感を覚える
浪人生に特有なのが、友達が大学で新生活を楽しむ様子をSNSや会話で耳にするたびに、「自分だけ取り残されているのでは」と感じやすいことです。
飲み会やサークル活動の写真を見て落ち込んだり、学園祭の話題についていけずに孤独を感じたりすることもあるでしょう。
また、自分の成績がなかなか伸びないときに他人の成功例を見ると、無性に不安や焦燥感が強まります。
このようにまとめ的な文言を装飾するのもありです。
人間関係やプレッシャーによるストレス
予備校には多くの受験生が集まるため、人間関係が煩わしくなることもあります。
切磋琢磨できる仲間がいるのはメリットですが、逆に競争心を煽られすぎてプレッシャーに押しつぶされるケースも少なくありません。
「周りはこんなに勉強しているのに、自分はまだ足りてないかも」と思い詰めたり、クラスメイトとのトラブルや比較で自信を失ったりすることもあるでしょう。
このようにまとめ的な文言を装飾するのもありです。
経済的負担が大きい
浪人や現役での通塾には、入学金や授業料などのまとまったお金が必要です。
これを家計に負担してもらっている場合、「これだけ払ってもらっているのに成果が出せなかったらどうしよう」とプレッシャーになるかもしれません。
自分でアルバイトしながら授業料を捻出している人にとっては、経済的負担が大きいほど、気持ちに余裕がなくなることもあります。
このようにまとめ的な文言を装飾するのもありです。
予備校に行かない場合のリスクと注意点
予備校に行かず、独学や別の学習サービスを利用する方法は悪い選択肢ではありません。
しかし、予備校ならではのメリットを手放すことで、入試情報の偏りやモチベーション維持の難しさなど、新たなリスクも生じます。
入試情報が偏りやすい
大手予備校には、大学別の分析や合格データなどの蓄積があります。
これらを利用することで、最新の入試傾向をつかみやすいのは大きなメリットです。
独学や映像授業だけに頼ると、どうしても情報量にばらつきが出る可能性があるでしょう。
もちろん、書店やインターネットで情報は得られますが、それを「どう整理し、どう対策につなげるか」は自分次第です。
モチベーションや進捗管理の難しさ
予備校に通わない場合、授業やテストがペースメーカーとなってくれることがなくなります。
自宅学習では、誰かに管理されるわけではない分、勉強の進捗を自己管理できる人とそうでない人で大きな差がつきやすいです。
忙しくなったりスランプに陥ったりすると、計画が崩れてそのまま立て直せないケースもあります。
自宅浪人を選ぶ際には、日々のスケジュールチェックや声かけをしてくれるサポート体制をどこかで確保できるかどうかを考えてみましょう。
2023年に東北大学法学部に合格した佐藤さんの場合
【自宅浪人で感じた壁】
私の場合、自分で現状分析を行い、大学受験から逆算してやるべきことを明確にした結果、毎日サボらずに自分の意思で勉強を続けられました。
しかし、自分の現状を客観視できない人や、やりたいことに流されてサボる人には完全独学は厳しいと思います。
勉強以外にも「毎日外に出る」などを目標にして、生活面を管理できる人でないと難しいでしょう。
- 自分の現状を客観視できない人
- 自分のやりたいことに流されてサボってしまう人
- 勉強の話を共有できる相手がいないと不安やストレスを感じる人
にとっては完全な独学による自宅浪人は向かないと思います。
また、私の場合は、浪人時代に受けた模試の判定がずっとA判定でした。
しかし、共通テスト本番に限ってうまく振るわず、最後の判定だけB判定でした。
共通テストでほとんどが決まる入試方式を検討していたので、本番に転けたことは想定外で、正直とても落ち込みました。
そんな時に、受験まで伴走してくれるメンターがいれば、きっと心の支えになったと思います。
↑吹き出し部分がタイトルの役割を果たしているので、タイトルボックスを使う方が一般的ではあります!修正例↓
予備校に行きたくないと感じたときの対処法
「もう行きたくない」という思いが強まったとき、すぐに退塾を決めるのではなく、まずは気持ちを落ち着けて状況を見直してみましょう。
ここでは、悩みを整理し、少しでも気持ちを軽くするための具体的な対処法を紹介します。
まずは自分の気持ちを整理する
最初にやるべきことは、自分が「なぜ行きたくないのか」を明確にすることです。
授業の質なのか、人間関係なのか、経済面なのか……原因を言葉にするだけで、対策がぐっと立てやすくなります。
悩みを紙に書き出したり、日記をつけたりして客観的に見つめ直すと「意外と簡単に解決できる部分もあるかも」と気づくことがあります。
思考の整理ができると、次にどう行動すればいいのかがクリアになってくるでしょう。
↑まとめ的な文言なので、こういう装飾もありです。
(ただの文章が4文続くので、何かしら装飾できないかなという目線で見ていました。)修正例↓
家族や友人に正直に打ち明ける
人に悩みを話すのは勇気がいることですが、家族や信頼できる友人に打ち明けることで、大きなサポートが得られる場合があります。
自分だけでは気づけなかった視点や、周りの人が既に知っている情報を教えてもらえることもあるでしょう。
また、人に話すことでストレスが軽減され、「もう少し頑張ってみよう」という気持ちが湧いてくることも珍しくありません。
予備校のチューターや学校の先生など、受験について相談しやすい相手に話を聞いてもらうのも有効です。
ワンポイントアドバイス的なところなので、吹き出しを使ってみるとちょうど良いかもです。顔が見えると安心感が与えられるので。(ただの文章が4文続くので、何かしら装飾できないかなという目線で見ていました。)修正例↓
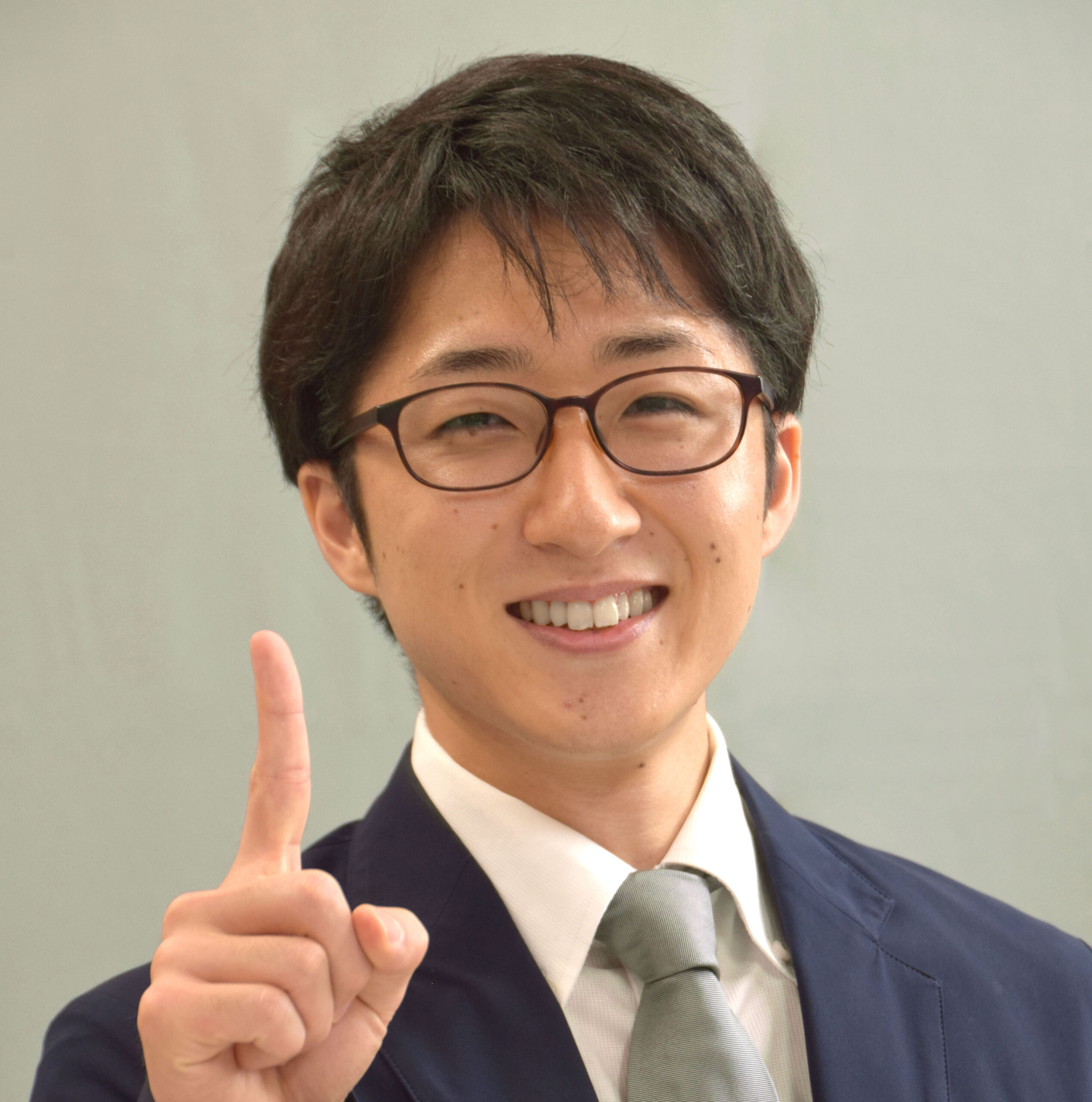
塾長 内田
予備校のチューターや学校の先生など、受験について相談しやすい相手に話を聞いてもらうのも有効です。
一度休む・違うアプローチを試す
現役生であれば、思い切って1日休む・数日間自宅学習に切り替えてみるなど、「予備校に行かない期間」を意識的につくるのも効果的です。
スタディサプリなどのオンライン講義を試したり、図書館で過去問を解いたりと、別の方法で勉強をしてみると気分転換にもなります。
浪人生であっても、あまりにモチベーションが下がっているなら、一旦ペースを落として「自分に合った方法」を探ってみましょう。
「何から始めればいいのかわからない」方は、オンライン個別指導塾の東大毎日塾を利用するなど、プロの力を借りるのも一つの手です。
\今だけ無料体験あり/
無料体験は毎月10人限定
予備校を続ける場合の対処法
「やっぱり予備校を続けよう」と思い直したなら、現状の問題点をはっきりさせて改善策を探りましょう。
授業の選び方や通学の仕方、人間関係への対処法などを工夫すれば、思いがけず環境が好転することがあります。
講師やチューターに相談する
クラスのレベルが合わないならクラス替えをお願いできないか、苦手科目の追加サポートは受けられないかなど、講師やチューターに直接相談してみましょう。
予備校によってはコース変更や別途の個別指導が用意されている場合もあります。
一人で悩んでいると「もうダメだ」と思い詰めてしまいがちですが、意外と簡単に解決策が見つかることもあります。
まとめ的に行動を促す文章なのでこういう装飾もありです。
自習時間を増やし、学習計画を見直す
得意科目は自主学習に回し、苦手科目を中心に授業を受けるなど、授業の「取捨選択」をしてみるのも有効です。
そうすることで通学時間や授業コマ数を減らし、自分にとって本当に必要な勉強に集中しやすくなります。
また、学習計画を自分で立て直すことで、「言われるがままに授業を受けていた」状態から抜け出せる場合があります。
自分の意思で勉強を進められるようになると、予備校の環境も無理なく活用できるはずです。
予備校に行きたくないときに検討したい勉強スタイル
「もう予備校には行きたくない」という思いが明確になったなら、自分に合った別の学習方法を検討してみましょう。
ここでは、独学やオンライン指導など、具体的な学習スタイルのポイントを解説します。
自主学習の環境づくり
独学で成果を出すためには、まず勉強場所を整備することが重要です。
自宅や図書館など、自分が集中しやすい環境を確保しましょう。スマホの通知やSNSをオフにするなど、気が散る要因をできる限り排除するのがコツです。
ただし、家族の生活リズムや誘惑が多い場所だと、思うように集中できない場合もあります。
その場合は、有料自習室やカフェを併用するなど、自分が没頭できる空間を探す工夫が必要です。
勉強スケジュールを立てる・見直す
予備校のカリキュラムに縛られない利点を活かすためには、自らスケジュールを組み立てる力が欠かせません。
特に、予備校に通っているいないにかかわらず、自分で教材選定をして、学習計画を立てることが必須です。
例えば、東大志望だからと言って、共通テストで6割くらいしか取れないのに、東大コースの授業をとっても伸びません。
共通テストで8割は取れるレベルの基礎力が固まっている人が受けて初めて、結果につながるのが東大コースの授業です。
↑ただの文章が5文続くので、装飾したいです。今回は具体例の背景を塗りつぶすと見やすくなります。修正例↓
例えば、東大志望だからと言って、共通テストで6割くらいしか取れないのに、東大コースの授業をとっても伸びません。
共通テストで8割は取れるレベルの基礎力が固まっている人が受けて初めて、結果につながるのが東大コースの授業です。
修正例ここまで
このように、予備校で志望校に合わせてコース選択をしていても、本当に必要な勉強は別にある可能性も大いにあるので、そこを自分で考えることは必須になります。
それよりは、自分に必要な勉強や計画を一緒に考えてくれる、学習管理型のコーチング塾の方が圧倒的におすすめです。
1週間単位、1日単位でタスクを細分化し、どの教科をどれだけ進めるか明確にしましょう。
大切なのは、進捗状況に合わせてこまめに見直すこと。
予定通り進まない日があっても、早めに計画を修正できれば大崩れは防げます。
常に「いま自分はどれくらいまで進んでいるのか」を把握できるようにしておきましょう。
↑急に何の話が始まったかわかりにくいので、タイトルをつけるとわかりやすくなります。そして、具体例として背景青塗りは直前で使ったので別の装飾でいきます。そして、冗長にならないようにテーマ的にまとめられるところを1段落にまとめました。修正例↓
1週間単位、1日単位でタスクを細分化し、どの教科をどれだけ進めるか明確にしましょう。
大切なのは、進捗状況に合わせてこまめに見直すこと。
予定通り進まない日があっても、早めに計画を修正できれば大崩れは防げます。
常に「いま自分はどれくらいまで進んでいるのか」を把握できるようにしておきましょう。
映像授業や参考書を活用した独学
スタディサプリのような映像授業や、講義形式の参考書をメインに学習する独学スタイルは、自分のペースで好きなだけ進められるのが魅力です。
苦手単元を何度も見直せるなど、予備校の一斉授業にはない柔軟さがあります。
大事なポイントなので、このように装飾するのもありです。↓
友人同士で教え合ったり、オンラインで解説サービスを利用したりして、独学の弱点を補える工夫をしましょう。
学習管理型オンラインコーチング塾を活用
「何をどれくらい勉強すればいいか分からない」「ついサボってしまう」といった悩みがあるなら、学習管理型のオンラインコーチング塾も選択肢になります。
たとえば東大毎日塾では、オーダーメイドの学習計画と日々の進捗管理、24時間いつでも質問できる仕組みをオンライン完結で提供しています。
↑ただの文章が4文続くので、何かしら変化させられないか考えてみます。今回は箇条書きが使えそうです。修正例↓
たとえば東大毎日塾では
- オーダーメイドの学習計画
- 日々の進捗管理
- 24時間いつでも質問できる仕組み
をオンライン完結で提供しています。
修正例終わり
相手のニーズを捉える重要な文言なので太字にするのもありです↓
予備校通いに比べて柔軟性が高く、完全な独学ほど孤独でもないため、「予備校は合わないけれどサポートは欲しい」という方に向いています。
まずは無料個別相談会で雰囲気を確かめ、予備校以外の可能性を具体的にイメージしてみるとよいでしょう。
\毎月10人限定/
ご入会を強制するものではございません
佐藤さんの体験談
【私が選んだハイブリッド学習】
浪人が決まってから、大手予備校2校の説明会に行きましたが、料金が高くて費用対効果が不透明に思えました。
最終的には個別指導+有料自習室+スタディサプリを組み合わせる方式に。
計画は自分で立て、個別指導の先生には解説や相談役をお願いし、模試や夏期講習だけは予備校を利用して外部の刺激を得るようにしました。
結果、自分のペースを保ちつつ、必要なサポートを得られたと感じています。
同様にタイトルブロック推奨です↑
予備校を辞めたいときはどうすればいい?円満に退塾するポイント
「もう予備校を辞めたい」と思ったら、正式な手続きを踏む必要があります。
ここでは、スムーズに退会するための基本的な流れを解説します。
引き留めに遭わずに円満に辞めるためのコツもあわせて紹介します。
正式な退会手続きの進め方
- STEP
契約書や規約を確認
まずは、入塾時に交わした契約書や規約を確認し、退会に関する条件や時期を把握しましょう。
塾によっては書面による申請が必要だったり、専用の退会フォームが用意されている場合があります。
- STEP
契約権限のある教室長や担当スタッフに直接伝える
手続きの際は、アルバイト講師だけでなく、契約権限のある教室長や担当スタッフに直接伝えることが大切です。
退会理由を簡潔に説明し、金銭面の精算や今後の手続きがどうなるかを明確に確認しておきましょう。
塾を辞める場合の注意点については、以下の記事でも紹介しています。
辞める際の伝え方なども詳しく説明していますので、参考にしていただければと思います。
↑内部/外部リンクを使いましょう。例↓
引き留められたくないときのコツ
引き留めを避けたいなら「すでに別の塾やサービスに入る予定です」とはっきり伝えるのが有効です。
相手も次の進路が決まっていると分かれば、深追いしづらくなります。
また、「自分には合わなかった」というスタンスで話すと、相手を否定するわけではないためトラブルになりにくいです。
退塾後に残っている教科書や教材の処分や、返金の有無なども忘れずに確認しておきましょう。
自分に合った学習スタイルを見極めよう
「予備校に行きたくない」という気持ちが起きた今こそ、自分の勉強法を見直すチャンスかもしれません。
学習ペースや周囲の環境、費用面などを総合的に判断しながら、あなたが納得して走り抜けられるスタイルを見つけましょう。
↓ただの文章が5文続いている状態で、かつこの文章は一番重要なので、以下のような装飾がおすすめです↓
↓日本語としておかしいので、修正します!(原稿の問題なので、今後気づいたら修正するくらいで大丈夫です。)改行もしています。
東大生の経験豊かなメンターが、あなたに合わせた学習プランと丁寧なサポートをどこにいても受けられます。
一人で悩んでいるなら、東大毎日塾の無料個別相談会を活用してみてください。受験のプロが、あなたの状況に合わせた学習プランを一緒に考え、個別サポートすることが可能です。
修正例ここから
東大生の経験豊かなメンターによる丁寧なサポートをどこにいても受けられます。
一人で悩んでいるなら、東大毎日塾の無料個別相談会を活用してみてください。
受験のプロが、あなたの状況に合わせた学習プランを一緒に考え、個別サポートしていきます!
修正例ここまで
\今だけ無料体験あり/
無料体験は毎月10人限定